
運転中の6AS11アンプ
複合管でQRPアンプを作る

運転中の6AS11アンプ
「田村さん、これで一度作ってみない?」
ずんぐりしたコンパクトロンが出てきました。複合管ですが何か電極が異様に多いような...見るとプレートが3枚入っています。カラーテレビ用の3極3つというのは見たことありますが、一つはビームの様です。
「何ですかこれ?」
「3極、3極、ビームだよ。」
私は面白いので早速2本購入しました。ビーム部は大きくて、良さそうな外観をしています。(プレートが平らで、ビーム電極が大きくいものは音が良い?)多分テレビの垂直出力用と思われます。外観と規格を以下に示します。
球外観・規格
6AS11外観 |
ユニット |
規格 |
|
|
|
Pentode |
Eb |
200V |
Pp |
5W |
||
Ec2 |
24mA |
||
Rk |
68 |
||
gm |
10500 |
||
rp |
70000 |
||
Triode1 |
Eb |
200V |
|
Ec |
2V |
||
u |
68 |
||
rp |
12.4K |
||
Triode2 |
Eb |
200V |
|
Ec |
2V |
||
u |
41 |
||
rp |
9.4K |
||
せっかくですから小さいケースに組みこんで可愛く仕上げることにしました。他に真空管などは立てず1本で片chとします。2本でステレオ構成とすると幾つか回路が考えられます。
検討の結果、差動入力を採用しました。以前6Y6で行った強NFと同じ構成の回路です。この回路を使用する場合、差動部、出力部ともにデータシートそのままの値を使用して問題ありません。ビーム部のバイアスはデータシート通りの68Ωを使用しました。NFに関してですがOP−Ampのゲイン決定と同じ様に行います。今回は手持ちの抵抗の関係で47倍としました。ただし、OP−Ampのような裸ゲインはありせん。よって計算より低いゲインとなります。以下に回路を示します。
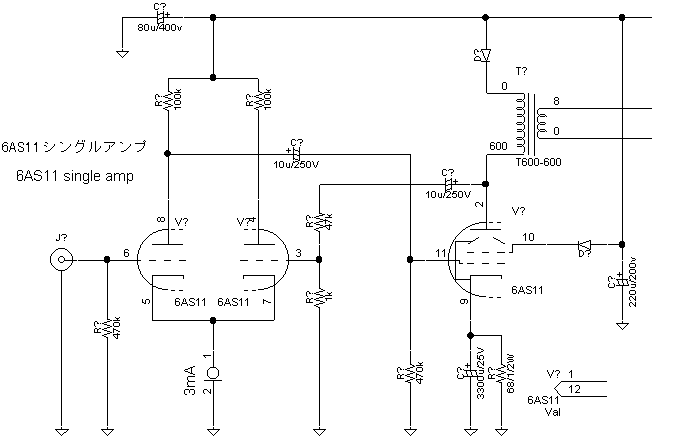
6Y6の時と同じ構成です
出力トランスは600Ω−8Ωを使用しました。NFを多く掛ければ600Ωでも問題ありません。更に、600Ωのトランスですと、DCRも小さく、周波数特性も良好で、電流も多く流せます。トランスは東栄T600−600を使用しました。
シャーシはタカチのYM−130を使用しました。6AN5で使用したシャーシの一つ上のサイズです。電源用のコネクタは6AN5と同じフィーダー中継用コネクタを使用しました。今回はシャーシに角穴を開けるのが大変なためケース上部に接着としました。
GNDはいつものようにベタ・アースとしました。穴あけ後銅箔シールを張り、カッターで穴の部分を切り取ります。使用したシールは某不要輻射測定サイトにあった試供品です。
配線で注意が必要なのは線の長さです。特に、ビーム部周辺の配線に関しては最短にしてください。ビーム部はバイアスが浅いため簡単に発振すると思います。部品間の配線を最短にするために、抵抗は全て1/4Wを使用しました。GNDに接地する部分はソケットの端子よりその真下のベタ・アースに配線します。カップリングは迷わずケミコンとしました。小型なので短い配線が可能です。
電源を入れて待つこと3分。早速、音楽信号を入力してみました。音は意外なほどあっさり出ました。聞きながら出力の位相などを確認、合わせをおこないました。その間30分。だいぶシャーシも暖まり、最初荒れていた音も落ち着いてきました。スピーカーをテスト用のPIMからパネルに切替えました。6AN5で驚いたのと同様に吃驚するほど良く鳴ります。6AN5超3と比べると、よりスッキリした清涼感のある音です。低域の感じは同じですが高域は6AN5超3より伸びていると思われます。今後、エージングが進むにつれ荒れた部分は収まると思います。今後が楽しみなアンプになりました。
6AS11は以外なほど高音質です。超3を既に何台か作られた方はぜひ試してみてください。少し毛色が変わって面白いと思います。

横向き
1999/06/09
田村
タムさんのページへ 手作りアンプのページへ